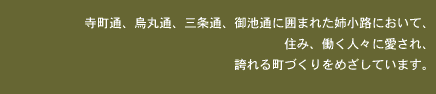
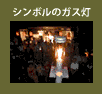


姉小路界隈には、名にし負う人たちの筆による看板が幾多あります。看板は「内なるものから外に対するものへの発信」(京大教授の三村浩史さん)です。文化と歴史をひそめて幾星霜を経た名だたる街角の看板から、その一部を…
* 地図の緑の場所をクリックすると詳しい地図が表示されます
 |
「御菓子司亀末廣」(姉小路通烏丸東入ル)
撮影:前田繁夫 ヒノキの一枚板である。額縁のように貸しの木型が周囲を取り囲む。ツル、ボタン、アユなどが。近代書道の先覚といわれた山本竟山(きょうざん)の書による。竟山は明治35年から8度中国に渡って学んだ。45年に岡崎に居を移す。京大内に学書道場を開く。門弟に佐々木惣一、湯川秀樹らが。竟山によって「関西の書風為に一変す」と評された。看板は先々代五代目が依頼したという。 |
「春芳堂」(姉小路通烏丸東入ル)
撮影:前田繁夫 リズム感のある草書だ。原書は、小さな表札の墨書である。大正5年6月の日付がある。すでに清新な画風で、日本画壇に揺るがぬ画境を確立していた栖鳳(せいほう)53歳の書だ。ケヤキの一枚板の看板にした。春芳堂は栖鳳お気に入りの表具屋だった。安政3年の創業である。初代は四条円山派の中島来章に学び、「李章」と号した画家だった。現当主の伏原桂造さんは五代目である。 | |
「柚味噌」(姉小路通烏丸東入ル)
撮影:前田繁夫 創業287年の803の看板だ。店内に「柚味噌」とあるケヤキの一枚板がかかる。書と篆(てん)刻をよくし、画家で陶芸家で料理家でもあった多才な魯山人(ろさんじん)が自らの書を彫った。「大観」の落款(かん)がある。表看板はその模刻だ。魯山人は上賀茂神社の社家に生まれた。初代民選京都市長の内貫勘三郎の嗣子清兵衛が支援した。京都に残した看板は7作だが、現存するのは2枚だ。 | |
 |
「泉屋市古商店」
撮影:前田繁夫 此の看板の制作は昭和12年10月頃であり、下京区寺町松原辺りの看板屋のものである。書体としての値打ちはないが、当時近辺に住んでいた有名書家が書いた手本集により彫られたものらしい。 |
 |
「柊家」(麩屋町通姉小路上ル)
撮影:前田繁夫 麩屋町通に、柊家、俵屋、炭屋の老舗旅館のご三家が並ぶ。行書体の、小さなケヤキの縦看板だ。透眼(とうがん)氏は昭和46年に結成した「新日本書道会辛亥支部」を主宰する。先代五代目夫人が教え子である。趣味で看板を彫刻している姉小路通寺町東のおそば屋さんの大久保清さんが彫った。柊屋は文政年間の創業だ。初代が下鴨神社の境内社の比良木神社を信仰していて、屋号とした。 |
 |
「彩雲堂」(姉小路麩屋町通東入ル)
撮影:前田繁夫 日本画専門絵具の製造発売のお店だ。現四代目の藤本築男さんによると、江戸時代末に京都の「伊勢屋」から分家したらしい。今も商標登録は、井桁の中に「勢」とある。明治半ばに現在地へ。近くにいた鉄斎に納品していた。鉄斎が「彩雲堂」と名付けて書を贈る。「彩雲」は李白の「早く白帝城を発す」の一節からとった。刻々に色が変化する早朝の雲のことだ。絵の具店らしい命名だ。 「蕎麦ほうる」(姉小路麩屋町東入る)
撮影:前田繁夫 河道屋は、そば、そばぼうろの老舗だ。小川町上長者町で菓子を商っていた。亨保年間に現住所へ。天香(てんこう)は明治38年に、一灯園を設立した。托(たく)鉢と奉仕の生活に入った時代だ。たまたま店を訪れた天香が先々代を知る。先代の植田正夫さん(現会長)の話しでは、子供のころの大正時代には看板はかかっていた、という。書かれたのは明治の末か。現当主貢太郎さんは十六代目だ。 |
 |
「亀屋良永」(寺町御池角)
撮影:前田繁夫 こだわりのない、温かい書だ。先代の下邑善代造さんが武者小路ファンだった。人を介して依頼した。武者小路、傘寿前後の書である。看板の制作は、木工作家の黒田楊園さんである。元の書に忠実に、墨のにじみを木に生かして文字が二段に彫ってある。御池通側には、篆書の看板がかかっている。泰東書道院を主宰した。山田正平による。62歳の筆という。 |
 |
「桂月堂」(寺町通姉小路下ル)
撮影:前田繁夫 力強い草書風の書体である。桂月堂の創業は、明治13年にさかのぼる。冠、矢立の製造の店を開いていた石野和三郎が、文明開化の時を迎えて神戸で4年間、ドイツ人に欧風菓子の製造を修業した。店を三条通寺町新京極東にもった。現在地には明治35年に移る。初代と親交が深かった鉄斎が書いた。初期の書より筆が太く、たくましい。 |